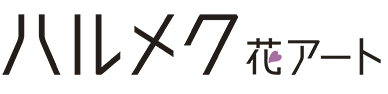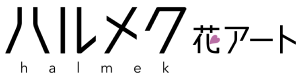2月4日の花 ウメ

Prunus mume
ウメ
バラ科サクラ属
・開花時期:1月~4月
・中国原産
・英名:Japanese apricot、Plum blossom
・花言葉:不屈の精神、高潔
・バラ科の落葉高木。花芽はモモと異なり、一節につき1個となるため、モモに比べ、開花時の華やかな印象は薄い。毎年2月から4月に5枚の花弁のある1~3㎝ほどの花を葉に先立って咲かせる。花の色は白、またはピンクから赤。樹木全体と花は主に鑑賞用に、実は食用とされ、枝や樹皮は染色に使われる。
・中国では紀元前から酸味料として用いられており、塩とともに最古の調味料だとされている。日本語でも使われるよい味加減や調整を意味する単語「塩梅(あんばい)」とは、元々はウメと塩による味付けがうまくいったことを示した言葉である。
・ウメの語源には諸説ある。ひとつは中国語の「梅」(マイあるいはメイ)の転という説で、伝来当時の日本人は、鼻音の前に軽い鼻音を重ねていた(東北方言などにその名残りがある)ため、meを/mme/(ンメ)のように発音していた。馬を(ンマ)と発音していたのと同じ。これが「ムメ」のように表記され、さらに読まれることで/mume/となり/ume/へと転訛した、というものである。
・中国原産。奈良時代の遣隋使(けんずいし)または遣唐使(けんとうし)が
中国から持ち帰ったようだ。「万葉集」の頃は白梅が、平安時代になると紅梅がもてはやされた。万葉集では梅について百首以上が詠まれており、植物の中では「萩」に次いで多い。
・梅紋(うめもん)は、ウメの花を図案化した日本の家紋である。その一種で「梅鉢(うめばち)」と呼ばれるものは、中心から放射線状に配置した花弁が太鼓の撥に似ていることに由来している。奈良時代に文様として用いられはじめ、菅原道真が梅の花を好んだことにより天満宮の神紋として用いられ始めたと考えられている。