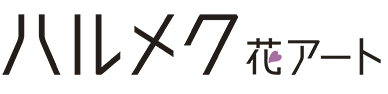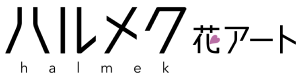2月26日の花 ユキヤナギ

ユキヤナギ
バラ科シモツケ属
・開花時期:3月~4月
・日本または中国原産
・英名: Thunberg’s meadowsweet
・花言葉:愛嬌、愛らしさ、賢明
・落葉低木。手を掛けなくても成長し、大きくなると1.5mほどの高さになる。地面の際から枝がいく本にも枝垂れて、細くぎざぎざのある葉をつける。葉が柳の葉に似て細長く、枝いっぱいに白い花を雪が積もったように咲かせるところから、また花がいっぱい散ったあとの地面にも雪がパラパラと積もったように見える。そのさまからユキヤナギ(雪柳)の和名がついた。
・公園や庭先でよく見かけるが、丈夫で適応力が強く病害虫が少ない、春に咲く花がきれい、比較的場所をとらずにまとまりがよいなど利点が多く、古くから庭園や生け花に利用されてきた。切り花としても普及している。また、つぼみがピンク色の「フジノピンク」という品種もある。
・学名の Spiraea(スピラエ)は、ギリシャ語の「speira(螺旋(らせん)、輪)」thunbergii はスウェーデンの植物学者「ツンベルク」の名前が語源。別名は「コゴメバナ(小米花)」。白い小花を米に見立てた。
・冬には紅葉する。枝が弓状に湾曲して真っ白い花を咲かせるのでユキヤナギ(雪柳)の名があるが、ヤナギのように枝が枝垂れると言うだけで、ヤナギの仲間ではない。中国名は「噴雪花」、名前の通り満開時は株全体が雪をかぶったように花で埋まる。岩肌や岩の裂け目などに生える様から、昔は「岩柳」とも呼ばれたようだ。
鉄橋のとどろきてやむ雪柳 (山口誓子)
花やの荷花をこぼすは雪柳 (大谷碧雲居)
雪柳ふぶくごとくに今や咳せく(石田波郷)
雪柳花みちて影やはらかき (沢木欣一)
たえず風やり過ごしをり雪柳 (高木晴子)