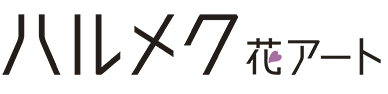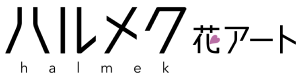3月27日の花 ムラサキケマン

ムラサキケマン
ケシ科キケマン属
・開花時期:4月~6月
・分布:日本全土
・和名:紫華鬘
・英名:Corydalis、Fumewort
・花言葉:「喜び」「あなたの助けになる」
・日本全国に分布する無毛の越年草。木陰などの直射日光の当たらない場所に生育し、低地の林縁や道端でも普通に見られる。
・全体がやわらかく、傷つけるとやや悪臭がある。茎はまっすぐに立ち、高さは20~50cmほどで、いくらか角ばっている。茎には斜め上に伸びる複数の葉が付く。それぞれ複葉で、三角状卵円形の小葉は扇形に近く、先端は丸く、縁に丸い鋸歯がある。葉質は薄くて柔らかく、つやを欠く。
・花は長さ12~20mm程度の赤紫色で、たまに白色または一部が白色になる。キケマン属に独特の筒状の花を咲かせ、豆に似た果実がなる。
・プロトピンを含む有毒植物である。誤って食すと、嘔吐、呼吸麻痺、臓麻痺などを引き起こす。ウスバシロチョウの幼虫の食草であるため、ウスバシロチョウも有毒の虫となる。
・山菜のシャク(ヤマニンジン)と生育場所や葉の形がよく似ているため、要注意である。
・学名のCorydalisは、花にヒバリの距のような距があることから、ギリシャ語でヒバリを意味するkorydalisに由来するといわれている。
・属名のキケマンは「黄色の華鬘(けまん)」の意味である。「華鬘」とは、古代インドで貴人に捧げられた生花のレイに起源があるといわれ、仏殿の長押(なげし)などに懸けられた荘厳具(しょうごんぐ。仏教の飾り)のことである。
・日本では生花の代わりに牛皮(ごひ)製、金属製、木製、玉製、絹製などの華鬘代(けまんしろ)が用いられ、団扇(うちわ)形といわれる横長の楕円形が多い。平安時代に京都の東寺(教王護国寺)に伝来したといわれる「牛皮華鬘」は、国宝である(奈良国立博物館所蔵)。