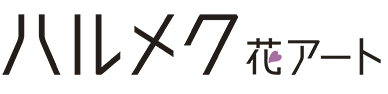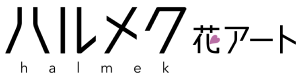2月18日の花 ゼンマイ

ゼンマイ
ゼンマイ科ゼンマイ属
・開花時期:花は咲かない
・日本全土に分布
・別名:デンダ、ヤマドリシダ
・花言葉:夢想、秘めたる若さ
・多年生シダ植物。山野に生える。水気の多いところを好み、渓流のそばや水路の脇などによく出現する。根茎は短く斜めから立つ。葉は高さ0.5~1m、新芽はきれいなうずまき状で、その表面は綿毛で覆われているが、成長すると全く毛はなくなる。
・新芽の渦巻から、平面の上の渦巻になっている形状のもの総じて「ゼンマイ」と称する。ゼンマイバネがその代表例で、これのことを省略してゼンマイと言うこともある。
・ゼンマイの語源としては「せんまき(千巻き)」に由来するという説、銭巻であり、巻いた姿が古銭に似るからとの説がある。
・若い葉は佃煮、お浸し、胡麻和え、煮物などにして食べる。かつての山里では棚田の石垣に一面に生えていた。
・山菜採りのマナーでは、ゼンマイには男ゼンマイ(胞子葉)と女ゼンマイ(栄養葉)があり、男ゼンマイを採るとその後再生しなくなるため採ってはならないとされている。
・新芽が平面上の螺旋形(渦巻き形)になる。その表面には綿毛が被さっている。スプラウトとして食用にするには根元を折り、表面の綿毛を取り去り、小葉をちぎって軸だけにし、ゆでてあく抜きし天日に干す。干しあがるまでに何度も手揉みをして柔らかくし、黒い縮緬状の状態で保存する。 天日で干したものを「赤干し」と呼び、松葉などの焚き火の煙で燻したものを「青干し」と呼ぶ。また、韓国料理ではナムルの材料として使われる。
・ゼンマイは、山菜として食用にする他、立ち姿や葉がたいへん美しいので、
切り花や庭園での観賞用としても活用される。ゼンマイとワラビの見分け方は、葉の先端がくるっと丸まって綿毛に覆われているのがゼンマイ、先端がこぶしのように丸まっているものがワラビである。