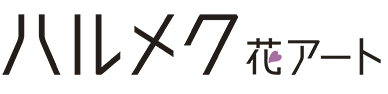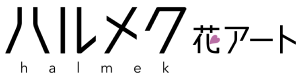3月16日の花 タチツボスミレ

タチツボスミレ
スミレ科スミレ属
・開花時期:3月~5月
・分布:日本全土
・和名:立壷菫
・別名:相撲取草(スモウトリグサ)
・北海道から沖縄にいたる、ほぼ日本全土の平地から低山に分布し、日当たりのよい道端や草原、森林、やぶなどに普通に見られる多年草である。
・数本から10本程度の茎を伸ばして、直径1~2cmの薄紫色の花が咲くが、咲き始めには茎はまだ短いため、根元から花が直接出ているように見える。茎はしだいに立ち上がり、高さは10~30cmになる。葉は先がとがった卵円形で、ハートのようにも見える。
・白い花のシロバナタチツボスミレ、花色が薄いピンクのサクラタチツボスミレ、白い花で距(花の後ろにある出っ張り)だけが紫色を帯びるオトメタチツボスミレ、海岸近くに生えて葉に光沢があるツヤスミレ、葉の葉脈に沿って赤色の斑が入るアカフタチツボスミレなどがある。
・日本には数多くの種類のスミレ属があるが、日本を代表するスミレといえば、タチツボスミレである。さまざまな種類のスミレが全国各地に見られるが、開花時期がほぼ同じのため混同しやすい。
・タチツボスミレとスミレの見分け方は、次の点に着目するとよい。
タチツボスミレの茎は、花の咲くころは地中で短いものの、成長すると地表に伸びて立ち上がってくる。葉は丸っこいハート形で、始めは根元から生え、茎が伸びるのにつれ葉も茎から生えてくる。花は薄紫色である。
一方、スミレの茎は立ち上がらない。葉は細長い矛型で、全て根本から出ている。花色は濃い紫である。
・別名の「相撲取草」は、2本の茎を絡めて、2人で引き合って勝負する遊びからきていると言われる。