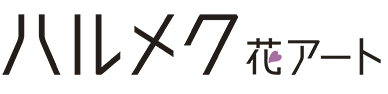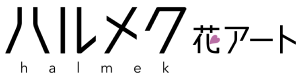2月9日の花 クロモジ

Lindera umbellate
クロモジ
クスノキ科クロモジ属
・開花時期:3月~4月
・日本原産
・英名:Kuromoji
・花言葉:誠実で控えめ
・クロモジは、クスノキ科の落葉低木。本州、四国、九州の低山や疎林の斜面に分布する。枝を高級楊枝の材料とし、楊枝自体も「黒文字」と呼ばれている。古くからこれを削って楊枝を作る。とくに根本に皮を残すのが香りがよいため、上品とされる。かの千利休もお茶菓子の爪楊枝はクロモジで作られたものを使用していた。現在でも、和菓子などではクロモジの楊枝が使われるところもある。千葉県の久留里地域ではクロモジの楊枝作りが明治期から副業として行われており、特産品化されている。
・黒文字の名は、若枝の表面にでる斑紋を文字に見立てたものといわれる。茎は高さ5m程度まで成長する。若枝は、はじめ毛があるが次第になくなり、緑色のすべすべした肌に、次第に黒い斑紋がでることが多い。古くなると次第にざらついた灰色の樹皮に覆われる。
・クロモジは、東北や北陸では鳥木と呼ばれ、狩りの獲物をクロモジの木の枝に刺し、神への供物とする風習がある。鷹狩で取った獲物を贈る際にクロモジの枝で結ぶことが多く、鳥柴とも呼ばれる。
・葉の展開と同時に開花する。黄緑色の小さな花が集まってつき、花柄には毛がある。
・クロモジの枝を編んでつくられる「黒文字垣」は、お湯をかけておくとよい香りを放つことから、お茶室の垣根などに使われてきた。
・枝を軽く削ると非常に爽やかな良い香りがする。精油は枝の樹皮に含まれており、和の精油として石鹸や香水、化粧品の香料として明治時代から日本人に親しまれてきた。また、枝と幹から取れる成分は養命酒でおなじみの「ウショウ」と呼ばれる生薬として活用されている。